別居は、心の距離だけでなく、お金の距離も生まれます。
「夫とはもうやっていけない」
「でも、別居したら生活費ってどうなるの?」
「家賃、光熱費…折半?全額自分持ち?」
私も当時まったくわからず、話し合いもろくにせずに家を出ました。結果――生活費の負担でモメて、後から弁護士に相談する羽目に。
今回は、別居後の生活費・家賃の分担について、私の体験をもとに“損をしないルール”をまとめたチェックガイドをお届けします。
まず知っておきたい!生活費の“法的”扱いとは?
実は、別居後であっても、法的には「夫婦」である限り、お互いには“扶養義務”があります。
つまり、
これを「婚姻費用(こんいんひよう)」といいます。
- Q婚姻費用とは?
- A
- 結婚生活を維持するための生活費(家賃、食費、光熱費、通信費など)
- 収入差が大きい場合、年収の高い方が多めに負担することが原則
- 取り決めがないまま別居すると、相手が一切支払わない可能性も
別居後の生活費・家賃:3つのケース別分担モデル

ケース1:家賃は別、生活費は一部負担(私の実体験)
私は別居後、自分でワンルームを借り、家賃・光熱費は完全に自分持ち。ただし、当時の夫(浮気してた側)が高収入だったため、調停を通して「婚姻費用」として月3万円を支払ってもらっていました。
- 家賃:自分持ち
- 光熱費:自分持ち
- 食費・日用品:自分持ち
- 婚姻費用:毎月3万円を夫から受け取り
👉 この形は「経済的自立はしているけど、正当な補助はもらいたい」人におすすめです。
ケース2:持ち家に一方が残る場合
たとえば、夫名義の持ち家に夫が住み、自分が出ていく場合。「住んでないのに住宅ローンを払うのか?」などの問題が出ます。
原則としては、
- 住んでいる側が維持費を負担
- ただし名義やローン契約者によっては「支払い義務だけ残る」可能性あり
ケース3:子どもなし+完全に別居生活を分離する場合
完全に経済も生活も独立させる場合、話し合いで取り決めを残すことが重要です。
- 生活費は原則、各自負担
- ただし、夫婦の財産形成中なので家計に使ったお金は「財産分与」の対象になる場合もあり
✅このパターンでは、「誰がどれだけ払ったかの記録」が後で役立ちます。
トラブルを防ぐための「事前の取り決め」チェックリスト

話し合いの記録は残す(メール or LINE)
- 手書きメモだけだとトラブル時に弱い
- できれば「いつ・どんな条件で別居するか」も含めてやりとりする
婚姻費用分担の話し合いをしておく
- 口頭ではなく、月額・支払い日・口座を明確に
- 応じてもらえない場合は、家庭裁判所に「婚姻費用分担請求調停」を申し立て可能
支出の記録を残す
- 家賃・光熱費・生活費の領収書・レシート・カード明細
- 離婚時の「財産分与」や「費用清算」の材料になる
損しない別居生活のために役立ったもの(私のおすすめ)

📍婚姻費用計算ツール(無料)
自分が受け取れる金額の目安を知っておくだけでも、交渉が楽になります。
🔎 離婚相談・法的サポート
モヤモヤを抱えたまま別居すると、ずっと後悔が残ります。
業界トップクラス、全国約1,000事務所、3,000人以上の専門家から、法律に関する様々なトラブル相談窓口を無料でできます。“離婚サポート”が含まれるので、専門家の意見をききたい場合はこちらがおすすめです。
📱支出記録アプリ(家計簿系)
別居中の費用記録は“自分を守る証拠”にもなります。
MoneyForwardなど、使い慣れているものでOK。支出の記録をつける習慣のなかった人は、記録を付ける習慣を身につけましょう。
まとめ:別れる前に、お金の話を“書き残して”おく勇気を
お金の話って、感情が絡むとすごく難しいです。でも、別れても、生活は続く。請求書は来る。家賃は発生する。
だからこそ、「生活費・家賃どうする?」という一見ドライな話題こそ、実は「あなた自身の人生を守るための、すごく優しい行為」なんだと私は思います。


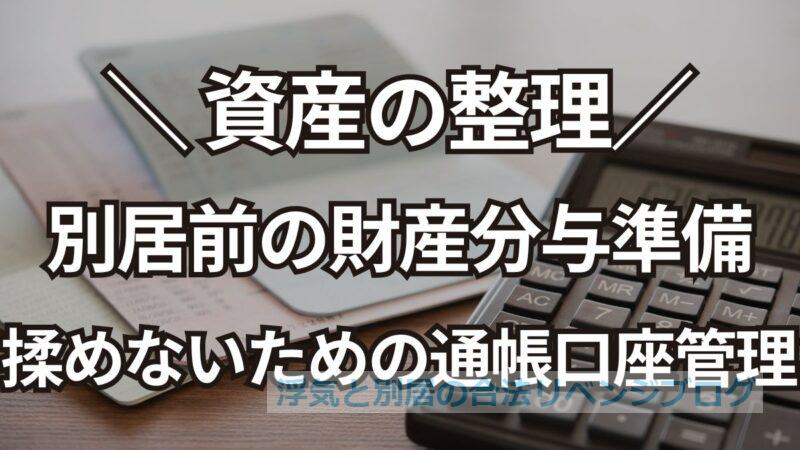
💬 私が過去の自分に伝えたいのはただひとつ:
「感情で動いて損するより、冷静に準備して“取り返さない”別居をしよう」ということです。